遺言制度のデジタル化?どう変わる?

「遺言」と聞いて、どのように感じるでしょうか?
「元気だから関係ない」、「財産が無いから関係ない」、「家族仲が良いから関係ない」……など。
実際に相続が発生し、「遺言があれば……」とおっしゃる方の中には、相続問題は自分には関係ないと思われていた方も少なくありません。
相続で揉めないために有効な対策である遺言制度について、今見直しが行われていることをご存知でしょうか?
今回は、「遺言制度のデジタル化」についてお伝えします。

「遺言」にも種類があるの?
「遺言は、何種類あるでしょう?」と言われて、ピンと来る方はどれ程いらっしゃるでしょうか。
遺言に種類があることを意識したことが無い、という方も少なくないと思います。
(この仕事をするまで考えたこともありませんでした……)
民法上、普通の方式3種類・特別の方式5種類が定められているのですが、今回は身近な2種類について簡単にご説明します。
①自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
「遺言書を書こう!」と考えた際に、一番身近な遺言の方式。
名前に「自筆」とある通り、遺言書の全文(財産目録除く)を「自分で書く」必要があります。
その他、記入した日付を正確に記載したり(〇月吉日などはNG)、署名が必要などの要件がありますが自分で作成でき費用もかからない方法。
ただし、遺言内容が要件に則っていないと無効になったり、改ざんされる恐れや遺言書を見つけてもらえない、死後に相続人による家庭裁判所での検認が必要などのデメリットもあります。
ちなみに、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、検認が不要など一部デメリットを解消することも可能です。
②公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
法律の専門家である「公証人」が作成、「公証役場」に保管してもらえる方式。
公証人に遺言内容を相談・遺言書にまとめてもらえることで、法的不備などで無効になる恐れを回避することが可能な信頼性の高い遺言です。
その他、改ざんや隠ぺいの恐れが無く、遺言者の死後相続人であれば遺言を確認することが可能で、家庭裁判所での検認も不要。
ただし、自筆証書遺言に比べて、費用がかかることや証人2名(相続人は不可)の立ち合いが必要など、気軽に作成するには少しハードルが高い方式です。
遺言制度のデジタル化って?
現代社会におけるデジタル化に合わせ、政府は行政のデジタル化を重要な課題
と位置付けています。
その中で現行の遺言制度についても、「自筆証書遺言制度のデジタル化」を掲げました。
具体的に、法務省は自筆証書遺言と同程度の信頼性が確保され、かつ簡便に遺言を作成できるように新たな方式を設けたり、自筆証書遺言書における押印の必要や自書を要求する範囲等について検討を行うことに。
(公正証書遺言手続きのデジタル化については、令和5年6月に公証人法改正)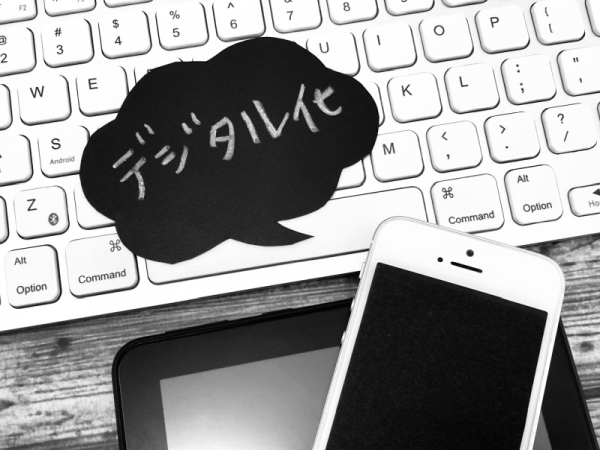
現在、年間の死者数が約150万人のところ、遺言書の検認件数は約2万件・自筆証書遺言の保管申請件数は約1万6千件・公正証書遺言作成件数は約11万件となっています。
自筆証書遺言の保管申請件数と公正証書遺言作成件数は、申請・作成時点の数のため単純に亡くなった150万人の内何人が遺言制度を利用していたか厳密には分かりません。
ただ、死者数に対して検認数・保管申請件数・公正証書遺言作成件数の合計が1割に満たないことを考えると、利用者数が多いとは言えない状況ではないでしょうか。
遺言制度をデジタル化することにより、遺言制度を利用しやすくなる可能性があります。
例えば、実際に公正証書遺言制度を利用する方は60代以上、特に70~80代が多く、自筆証書遺言を検討される方も同様の傾向があると推測されます。
比較的手軽とは言え、自筆証書遺言は「全文自筆」での記入が必要など、高齢者の方は身体的に自書が難しいなどハードルがあることも。
そのような場合でも、デジタル化の実現によって自書や押印などの負担が軽減されるかもしれません。
また、デジタルに詳しい比較的若い世代にも利用しやすくなるなど、遺言制度を利用へのハードルが低く・使いやすい制度になる可能性を秘めています。
デジタル化の課題・デメリットは?
メリットが多いから、早くデジタル化すればいいのに!というところですが、簡単が故に懸念事項も多く検討が進められています。
最近、莫大な遺産を残して亡くなった資産家が「市に全財産を残す」とした自筆証書遺言について、有効性が問われた裁判が話題となりました。
この裁判は、親族が「遺言書は資産家以外の人間が作成したもの」と訴えたもので、例え自筆であったとしても争いが生じることもあります。
このうような問題は、デジタル化によって手続きが簡易化できる反面、より問題となってくる可能性が高く十分な検討が必要に。
具体的には、以下のような点が検討課題に挙がっています。
●遺言の本文に相当する部分の在り方
デジタル化にあたり、具体的に遺言書の本文をどのように作成するか、という点です。
例えば、自書した書面をスキャンしてデジタル化、タッチペンやワープロソフトによる入力、録音・録画などでの入力などが考えられます。
作成の簡便化だけでなく、偽造や改変が行われるリスクを回避についても重要な検討事項と言えるでしょう。
●真正性を担保するための方式の在り方
前述の裁判の件でも問題となった、「本人が自分の意志で作成したかどうか」を判断する「真正性の担保」は重要な問題となります。
電子署名と合わせて、録音・録画を行うなど様々な方法が検討されています。
●保管制度の要否等
現行の自筆証書遺言では、自分で遺言を保管したり相続人に託す・法務局の保管制度を利用するなどの方法があります。
ただ、デジタル化をするにあたり、真正性の担保や偽装などを防ぐ観点からも遺言をどのように保管するかは重要な課題に。
以上のように、デジタル化の実用に向けては、より厳格な仕組みづくりなど検討する必要がある課題が山積みです。
デジタル化について、今後も動向を注意深く注視することが必要だと思われます。
いつからデジタル化されるの?
現状、検討が進められており報告書も出ておりますが、いつから実施されるかは未だ不透明な状態です。
デジタル化されるまで遺言作成を待とうかな、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ただ遺言は作成して終わりではなく、状況の変化に応じて見直しや変更を行うことも重要です。
特に相続人関して懸念事項がある方(相続人間でもめる可能性がある、法定相続人がいない、遺産の分け方を自分の希望通りにしたいなど)は、ひとまず現行制度にて遺言を作成しておくのはいかがでしょうか。
デジタル化が施行された際に、改めて遺言の見直しや方式の変更を検討する方法も。
当事務所では、公正証書遺言作成など生前対策の一環として遺言に関するご相談も受け付けております。
相続の専門家の目線から、様々なケースにおける対応についてご提案させていただきますので、当事務所の無料相談をぜひご利用ください。
【参照・関連サイト】
「遺言制度のデジタル化」「自筆証書遺言保管制度」について詳しくは、法務省ホームページ等でご確認ください。
・遺言制度の見直しにおける主な検討事項(法務省)※注1
・デジタル技術を活用した遺言制度の在り方に関する研究会報告書(法務省)※注1
※注1:法制審議会民法(遺言関係)部会第1回会議(令和6年4月16日開催)資料より
・自筆証書遺言保管制度(法務省)
※本記事の記載内容は、2024年6月現在の法令・情報等に基づいています。
